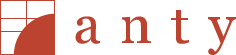輪島塗がどのようにしてはじまったのかは、裏付けとなる資料が少なく、はっきりとはわかっていません。しかし、現在の輪島塗に使われている珪藻土が、輪島周辺で出土した中世の漆器にも含まれていたこと、またいくつかの記録から、室町時代には漆器づくりが行われていたと考えられています。
漆器作りが発展した要因として、近隣にアテ、ケヤキ、ウルシ、輪島地の粉など、材料となる素材が豊富にあったことや気候風土が漆器作りに適していたこと、古くから日本海航路の寄港地として材料や製品の運搬に便利であったことなどがあげられますが、漆器の生産・販売にたずさわってきた多くの人々が、品質に誇りを持ち、技術を磨き続け、今日まで受け継いできたことも大きな理由の一つといえます。
これらを背景として、「椀講」や「頼母子講」と呼ばれる独特の販売方法を普及させつつ販路を拡大し、全国的に知れられるようになりました。

うるしとは漆の木から採取した樹液です。丈夫で艶やかな質感をもつ塗料となり、強力な接着剤にもなります。東アジアの国々に分布し、日本では数千年も前から利用してきました。漆の語源は「うるわし(麗し)」「うるむ(潤む)」ともいわれ、みずみずしい艶を表しています。
固まると酸やアルカリにも強く、数千年の時を超えるほどの耐久性を有しています。縄文時代の遺跡から出土した漆製品では、木地が朽ち果てたにもかかわらず、漆そのものは色鮮やかに保たれていることが確認されています。
その一方で、漆は大変デリケートな素材でもあります。採った時間や天候、場所、採り方によっても性質が変わってきます。一本の木から採れる漆の量は150gほど。椀数個分しか採れない、大変貴重な材料です。

自然の恵みである木材と漆で作った漆器は、ほとんどが天然素材であり、微小な生産エネルギーで、有害な物質を発生させることもなく、環境汚染や自然破壊が極めて少ない産物です。
漆の乾燥は、普通の化学塗料等と異なります。漆の成分が空気中の水分と反応し、硬化するのです。実はこの反応、漆器の完成後もゆっくりと進んでいます。よって、塗りあがって間もない製品は、できるだけ優しく扱ってください。
1年もすれば普通に使えるようになり、使い込んで3年も経つと深い底艶が出てきます。